検索結果で目立ちクリック率・順位向上に直結するタイトル&メタタグ最適化の即効ヒント
- タイトルを全角30文字以内にまとめる
検索結果で切れず意図が伝わりやすくなる
- 実際の検索数が多いキーワードを最低1語必ず含める
ユーザー流入数増、露出チャンス広がる
- メタディスクリプションは120字程度でページ内容と解決策を端的に記載
クリック率向上、無駄な表示や誤解防止
- (月1回以上) サーチコンソール等でCTR・表示順位変化をチェックし改善継続
"放置=機会損失"小さな調整でも成果倍増可
名前なきWebページとメタタグの迷走
完璧なスニペットを作成すると、いやまあ実際は難しいことも多いけど、可視性とかクリック数、それに「人と人とのつながり」…そういうのが本当に大きく変わることがあるんだよね。ああ、でも毎回うまくいくとは限らないって話も聞いたことがあるし…。で、デジタルマーケティングの世界だとさ、メタタグとメタディスクリプションが要みたいになってて、自社の色んな製品をオンライン顧客に伝えるためにはウェブサイトでその役割をちゃんと果たしているんだ。具体例を挙げて、とか言われると急に考え込みたくなるけど、まあ、本質的な理由やウェブページでわざわざ使う意味についてちょっと整理してみようかな。
新生児って最初は名前がないよね?それ自体は別に珍しくもない。でも…えっと、HTML生成されたばかりのウェブページにももしメタタグや説明文(ディスクリプション)が付いてなかったら、ランディングページ訪れたお客さんは、その内容とか何が得られるかハッキリ想像できなくて困っちゃう場面も当然出てくると思う。ま、いいか。そのへんから察してほしいんだけど…。だからこそオンライン上で目立つためにも、自分たちの「アイデンティティ」をちゃんと見せるためにも、この二つ——つまりメタタグとディスクリプション——が必要なんだよね。本記事ではそのへん掘り下げて、デジタルマーケティング領域における両者の基礎的な概念についてゆっくり解説していこうと思います。疲れてても、一応気合入れて書いてみます…。
## 目次
1. メタタグとメタディスクリプション
2. オンページ最適化とオフページ最適化
3. バックリンク
## メタタグとメタディスクリプション
**HTML**内で利用されているこの種のタグは、おおむね160文字程度でウェブページ全体の中身を簡潔にまとめるものです。ほんとうにそれだけ?って思うけど…。検索エンジンによっては、この「メタディスクリプション」というラベル付きの説明文をそのまま検索結果一覧画面で表示する場合もあったりするので(いや全部じゃないらしい)、ユーザー側としてはクリックする前からなんとなくそのページの概要とか雰囲気まで把握できたりする仕組みなんですよね。これについて具体例として挙げるなら…あれ?ちょっと待った、有名SEOブログたちはどう見解しているっけ?彼ら自身、本当にこのタグ活用してたりする?導入理由なんかも踏まえて話した方がいい気分になってきました。結局、「何故使われているか」というところまで考えずにはいられないし…。
新生児って最初は名前がないよね?それ自体は別に珍しくもない。でも…えっと、HTML生成されたばかりのウェブページにももしメタタグや説明文(ディスクリプション)が付いてなかったら、ランディングページ訪れたお客さんは、その内容とか何が得られるかハッキリ想像できなくて困っちゃう場面も当然出てくると思う。ま、いいか。そのへんから察してほしいんだけど…。だからこそオンライン上で目立つためにも、自分たちの「アイデンティティ」をちゃんと見せるためにも、この二つ——つまりメタタグとディスクリプション——が必要なんだよね。本記事ではそのへん掘り下げて、デジタルマーケティング領域における両者の基礎的な概念についてゆっくり解説していこうと思います。疲れてても、一応気合入れて書いてみます…。
## 目次
1. メタタグとメタディスクリプション
2. オンページ最適化とオフページ最適化
3. バックリンク
## メタタグとメタディスクリプション
**HTML**内で利用されているこの種のタグは、おおむね160文字程度でウェブページ全体の中身を簡潔にまとめるものです。ほんとうにそれだけ?って思うけど…。検索エンジンによっては、この「メタディスクリプション」というラベル付きの説明文をそのまま検索結果一覧画面で表示する場合もあったりするので(いや全部じゃないらしい)、ユーザー側としてはクリックする前からなんとなくそのページの概要とか雰囲気まで把握できたりする仕組みなんですよね。これについて具体例として挙げるなら…あれ?ちょっと待った、有名SEOブログたちはどう見解しているっけ?彼ら自身、本当にこのタグ活用してたりする?導入理由なんかも踏まえて話した方がいい気分になってきました。結局、「何故使われているか」というところまで考えずにはいられないし…。
Googleの断片、SEO界隈の呟きと本音
メタディスクリプションの例や検索エンジンでの使い方について、ちょっと見てみようかなと思って書き始めたんだけど、気がついたら窓の外に猫がいて…いや、それはさておき、本題に戻ります。Googleでよく見るメタディスクリプションというものは、name="description" content="Search the world's information, including web pages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for." こういう感じなんですよね。うーん、とりあえずこの文だとスペースも含めて159文字ぴったりなんだとか。ま、細かい話だけど。
それから、Googleのメタディスクリプションって主要な3つの検索エンジンでも同じように表示されるんですよ。まあ、そのへんどうでもいい人もいるかもしれないけど…。ただ、多くのSEO担当者は「もしこれがランキングアルゴリズムには無関係なら何で使う必要ある?」みたいな疑問を持ったりするらしい。でも実際、「検索エンジンで順位アップを狙うためじゃなく、自分たちのビジネスにおけるコンバージョン要素として捉えてみて」と答えることができる、と個人的には思います。
いや、それより最近コーヒー飲みすぎかな…また脱線したので戻りますね。それとウェブサイト内ページだったりホームページだったりブログ記事などにも依然としてメタディスクリプションって重要視される理由はいくつかあります。そのひとつ――**理由1 -** 検索結果でキーワード部分が太字になる点です。ま、いいか。
それから、Googleのメタディスクリプションって主要な3つの検索エンジンでも同じように表示されるんですよ。まあ、そのへんどうでもいい人もいるかもしれないけど…。ただ、多くのSEO担当者は「もしこれがランキングアルゴリズムには無関係なら何で使う必要ある?」みたいな疑問を持ったりするらしい。でも実際、「検索エンジンで順位アップを狙うためじゃなく、自分たちのビジネスにおけるコンバージョン要素として捉えてみて」と答えることができる、と個人的には思います。
いや、それより最近コーヒー飲みすぎかな…また脱線したので戻りますね。それとウェブサイト内ページだったりホームページだったりブログ記事などにも依然としてメタディスクリプションって重要視される理由はいくつかあります。そのひとつ――**理由1 -** 検索結果でキーワード部分が太字になる点です。ま、いいか。

太字キーワード?クリック誘導が狙い
SNSもブックマークも説明文頼り?
見出しの主な目的って、まあ…テーマを強調することなんだけど、それが全てじゃない気もするんだよね。えっと、とりあえず検索エンジンはページ内の他のコンテンツより、やっぱり見出しに重きを置くらしい。そんな気がしてならない。というか、自分でも何度も「見出し大事」って言い聞かせてるけど、本当にそれだけなのかな、と不安になったりする。でもオンページSEO的には、まずページ全体の構成がちゃんとしてる前提で、特に見出しを意識して注力したほうがいいっていう話になるんだよね…。ま、そういうこと。
### URL構造
うーん…URL構造について語ろうとすると急に眠くなる。専門家たちはURL安定性をかなり重視しているようです(…本当に?いや多分)。プロフェッショナルは可能な限りURL変更は避けつつ維持すべきだと勧めていて、そのこだわりには一種の執念みたいなものさえ感じる時もある。ただターゲットキーワードをURL内に盛り込む工夫は必要不可欠っぽい。それから仕方なくURLを変える場合、新しいURLへリダイレクト処理を施すべしという意見も多いですね。ここまで書いておいて思ったけど、大抵の場合これで困らないので安心してほしい…たぶん。
### 説明文
画像につける説明文――altテキストとか――これもオンページSEOでは推奨されているわけで。「一枚一枚全部ラベル名考えるとか面倒くさい」と思いつつ、実際それぞれ適切な説明文付与が最善らしい。でも関連性高いキーワードや説明文って結局検索エンジン側にもWebページ全体テーマや内容理解に役立つかもしれないので、おざなりにはできない。不思議なのは時々、本当に alt テキスト書いた効果ある?とか疑問湧く瞬間。でもまあ地味ながら重要だから手抜き厳禁です…。
### URL構造
うーん…URL構造について語ろうとすると急に眠くなる。専門家たちはURL安定性をかなり重視しているようです(…本当に?いや多分)。プロフェッショナルは可能な限りURL変更は避けつつ維持すべきだと勧めていて、そのこだわりには一種の執念みたいなものさえ感じる時もある。ただターゲットキーワードをURL内に盛り込む工夫は必要不可欠っぽい。それから仕方なくURLを変える場合、新しいURLへリダイレクト処理を施すべしという意見も多いですね。ここまで書いておいて思ったけど、大抵の場合これで困らないので安心してほしい…たぶん。
### 説明文
画像につける説明文――altテキストとか――これもオンページSEOでは推奨されているわけで。「一枚一枚全部ラベル名考えるとか面倒くさい」と思いつつ、実際それぞれ適切な説明文付与が最善らしい。でも関連性高いキーワードや説明文って結局検索エンジン側にもWebページ全体テーマや内容理解に役立つかもしれないので、おざなりにはできない。不思議なのは時々、本当に alt テキスト書いた効果ある?とか疑問湧く瞬間。でもまあ地味ながら重要だから手抜き厳禁です…。
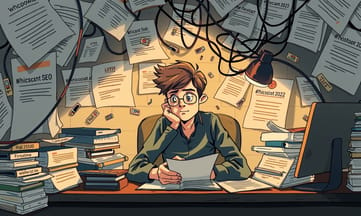
タイトル・見出しで踊るキーワード選び方雑感
### キーワード密度
キーワードの選び方とその密度って、サイト開発ではまあ…悩ましい問題だよね。うーん、最近はAIでも何でも「最適解」を求めがちだけど、結局はオンページ最適化とかで調整していくものなんだろうなと思ったり。あ、話が逸れた。最良のやり方としては、やっぱりキーワードの正しい選定と長さを考慮することが基本になる。「それだけ?」と思うかもしれないけど、意外と奥深い。ページ全体の内容にちゃんと沿った語句を使うのが推奨されているし…ま、いいか。あとキーワードはできるだけ短く保つこと、それも重要らしい。
### キーワード配置
で、そのキーワードの使い方とか配置も…実はかなり大事な要素だったりする。えっと、この部分についてもオンページSEOがしっかり管理してくれるっていう話をよく聞くけど、本当に全部任せていいのかな?いや、ごめん戻すね。本筋は、キーワードをうまい位置やリンク先に置く方法があって、それらはウェブサイトごとの背景情報とか関連情報を参考にしながらSEO専門家たちが検討してるアプローチだということ。
### ページ読み込み速度
ページ読み込み速度は…まあ当然だけど適切じゃなきゃ困るよなあとぼんやり思う。ユーザー体験を良くしたい気持ちはみんな同じだし、ウェブサイトや各ページを定期的に最適化しておかないと、有用性ってすぐ失われちゃう気がする。ああそうそう、この地道な実践こそが検索エンジン結果ページで上位表示される可能性につながる、と言われているけど本当なのかな、とふと思った。
### ページコンテンツ
ページのコンテンツ自体が一番大事な要素には違いないんだけど…突然話題変えてごめん。でも、本当に中身次第なんだよね。不安になる日もある。でも結局そこに尽きる、とまた元に戻す自分。
キーワードの選び方とその密度って、サイト開発ではまあ…悩ましい問題だよね。うーん、最近はAIでも何でも「最適解」を求めがちだけど、結局はオンページ最適化とかで調整していくものなんだろうなと思ったり。あ、話が逸れた。最良のやり方としては、やっぱりキーワードの正しい選定と長さを考慮することが基本になる。「それだけ?」と思うかもしれないけど、意外と奥深い。ページ全体の内容にちゃんと沿った語句を使うのが推奨されているし…ま、いいか。あとキーワードはできるだけ短く保つこと、それも重要らしい。
### キーワード配置
で、そのキーワードの使い方とか配置も…実はかなり大事な要素だったりする。えっと、この部分についてもオンページSEOがしっかり管理してくれるっていう話をよく聞くけど、本当に全部任せていいのかな?いや、ごめん戻すね。本筋は、キーワードをうまい位置やリンク先に置く方法があって、それらはウェブサイトごとの背景情報とか関連情報を参考にしながらSEO専門家たちが検討してるアプローチだということ。
### ページ読み込み速度
ページ読み込み速度は…まあ当然だけど適切じゃなきゃ困るよなあとぼんやり思う。ユーザー体験を良くしたい気持ちはみんな同じだし、ウェブサイトや各ページを定期的に最適化しておかないと、有用性ってすぐ失われちゃう気がする。ああそうそう、この地道な実践こそが検索エンジン結果ページで上位表示される可能性につながる、と言われているけど本当なのかな、とふと思った。
### ページコンテンツ
ページのコンテンツ自体が一番大事な要素には違いないんだけど…突然話題変えてごめん。でも、本当に中身次第なんだよね。不安になる日もある。でも結局そこに尽きる、とまた元に戻す自分。
URL構造いじらず転送、画像ラベルは面倒だけど大事かも
ウェブサイトって、その人気とか成功が結局コンテンツの質に左右される、なんて言われがちだけど――本当にそうなのかね。いや、まあたしかに、自分が何か調べものしているとき、有用で詳しい情報を見つけられると助かったりするし、「あー、やっぱり中身だよな」って納得しちゃうんだけども。ま、それでも内容が分かりやすくて読みやすいことは大事だと思う。…あれ? 今朝コーヒー飲んだっけ? ともかく、ページごとの明瞭さとか親切さは、本当に読む人間側からすると必要不可欠なんじゃないかな、と最近よく思うんだ。
### 内部リンク
内部リンクって実際どうなんだろうね、とぼんやり考えたりする。でも基盤という意味では確かに重要らしい(まあ自分も迷子になるタイプなので…)。ユーザーがスムーズにウェブサイト内を移動できるには、この内部リンクの存在感はでかいよね。その上で訪問者が関連ページからも追加情報を拾えるのだから、一種の案内板みたいな働きをしている気もする。ところで急に空腹になったぞ…。話戻すと、ホームページ一極集中ではなく、それぞれ個別のページにもアクセス数アップにつながる場合があるわけだから侮れない。それからオンページSEOによって検索エンジン側も発信元や各ウェブページのインデックス化、それにレイアウトまで特定しやすくなるようで、最終的には検索結果ページで順位付けされてしまう感じかな。まあ理不尽な部分もある気はする。
## オフページSEO
オフページSEOについて考えてみると、自分のウェブサイト上以外でする活動全部と言えるらしい。本当になんでもアリなのか少し疑問だけど…例えばソーシャルメディアだったりリンク構築だったり、更にはブログとかフォーラム参加まで含まれていて広範囲。一瞬「これ意味ある?」と思いそうだけど、有効なSEO戦略としてバックリンク作成が挙げられること多い。それによってドメイン全体および各個別ページの権威性向上につながったり――とまぁ理屈では聞く。ただ現実世界じゃ思い通り行かない日ばっかな気もしなくない。でもまだ眠気取れてないな…。
### 内部リンク
内部リンクって実際どうなんだろうね、とぼんやり考えたりする。でも基盤という意味では確かに重要らしい(まあ自分も迷子になるタイプなので…)。ユーザーがスムーズにウェブサイト内を移動できるには、この内部リンクの存在感はでかいよね。その上で訪問者が関連ページからも追加情報を拾えるのだから、一種の案内板みたいな働きをしている気もする。ところで急に空腹になったぞ…。話戻すと、ホームページ一極集中ではなく、それぞれ個別のページにもアクセス数アップにつながる場合があるわけだから侮れない。それからオンページSEOによって検索エンジン側も発信元や各ウェブページのインデックス化、それにレイアウトまで特定しやすくなるようで、最終的には検索結果ページで順位付けされてしまう感じかな。まあ理不尽な部分もある気はする。
## オフページSEO
オフページSEOについて考えてみると、自分のウェブサイト上以外でする活動全部と言えるらしい。本当になんでもアリなのか少し疑問だけど…例えばソーシャルメディアだったりリンク構築だったり、更にはブログとかフォーラム参加まで含まれていて広範囲。一瞬「これ意味ある?」と思いそうだけど、有効なSEO戦略としてバックリンク作成が挙げられること多い。それによってドメイン全体および各個別ページの権威性向上につながったり――とまぁ理屈では聞く。ただ現実世界じゃ思い通り行かない日ばっかな気もしなくない。でもまだ眠気取れてないな…。

密度や配置より、結局中身が問われる話(速度含む)
バスタブに水を入れる例について、えっと…考えてみたんだけど、なんかこう、うまく説明できるかな。まず最初に、バスタブの中にいくつかゴム製のアヒルをぽちゃんと浮かべてみる。あ、いや、実際はまだ水が入ってないからアヒルは底でじっとしてるわけ。でもね、水を注ぎ始めたらどうなる?当然ながらアヒルたちは水面までふわっと浮き上がってくるよね。
この時のアヒルをウェブページ、水をバックリンクだと思ってほしいんだ。うーん、ちょっとややこしいかもしれないけど…。つまりさ、最初はバスタブの底(まあベースレベル的な場所)に置かれていたゴム製のアヒルが、水位が上昇することで自然と高い位置へ押し上げられるような現象になる。ああ、ここまで言って何が言いたかったんだっけ。そうそう、これと同じことがオフサイト最適化でも起きたりするんだよね。
ウェブサイトの人気とかページランクの活動向上とか…この前述したゴム製アヒルと水の話が案外当てはまる場合もあるらしい。いや、本当にそれだけなの?と思うかもしれないけど、自分でもたぶんそうなんじゃないかなという感じで…。で、「ドメインオーソリティ」ってパラメータがあるでしょう、それは自分のウェブサイトが他所と比べてどれくらい「権威性」があるか示すものなんだよね。
この話ではページランクという概念も出てきたけど、簡単に言えば自分のウェブサイトへのリンク数が多いほどそのページランクも比例して高くなる傾向がある―まあ、一概には言えないけど、そこそこ当たってる気もする。しかし途中で気になったけど…オフページSEOで主な要素となるものにはバックリンクの質、それから自分のウェブサイト/ウェブページへのバックリンク数、この二つが重要視されているっぽい。それでいて、じゃあ具体的にどうやって自身のウェブサイト/ウェブページへリンクを作ればいいのか、その方法も下記みたいな形で存在しているわけだけど――まあ、その話はまた別途まとめたいな、と今思った次第です。
この時のアヒルをウェブページ、水をバックリンクだと思ってほしいんだ。うーん、ちょっとややこしいかもしれないけど…。つまりさ、最初はバスタブの底(まあベースレベル的な場所)に置かれていたゴム製のアヒルが、水位が上昇することで自然と高い位置へ押し上げられるような現象になる。ああ、ここまで言って何が言いたかったんだっけ。そうそう、これと同じことがオフサイト最適化でも起きたりするんだよね。
ウェブサイトの人気とかページランクの活動向上とか…この前述したゴム製アヒルと水の話が案外当てはまる場合もあるらしい。いや、本当にそれだけなの?と思うかもしれないけど、自分でもたぶんそうなんじゃないかなという感じで…。で、「ドメインオーソリティ」ってパラメータがあるでしょう、それは自分のウェブサイトが他所と比べてどれくらい「権威性」があるか示すものなんだよね。
この話ではページランクという概念も出てきたけど、簡単に言えば自分のウェブサイトへのリンク数が多いほどそのページランクも比例して高くなる傾向がある―まあ、一概には言えないけど、そこそこ当たってる気もする。しかし途中で気になったけど…オフページSEOで主な要素となるものにはバックリンクの質、それから自分のウェブサイト/ウェブページへのバックリンク数、この二つが重要視されているっぽい。それでいて、じゃあ具体的にどうやって自身のウェブサイト/ウェブページへリンクを作ればいいのか、その方法も下記みたいな形で存在しているわけだけど――まあ、その話はまた別途まとめたいな、と今思った次第です。
リンクで巡回…内部構造と検索エンジンの気まぐれガイド
優れたコンテンツを作成すれば、まあ、たぶんだけど、多くの人がそこから情報を得てくれる可能性はかなり高まると思う。で、その結果として自然にリンクされるケースもあるわけで……あ、ちょっと待って、いきなり話が飛びそうになった。でも結局はみんな自分が興味あるものしか見ないしね。
最近だとソーシャルメディアの存在感が大きくてさ、誰か一人でもシェアしてくれたら、それが何となく他の人にも伝播していって――うーん、不思議な現象だけど――最終的にリンクにつながることも割とあるっぽい。SNS疲れとか言われてもいるけど、それでも拡散力は馬鹿にできない。
また、業界内の有名なインフルエンサー? 彼らにメール送ったりデジタルマーケティングで接触したりすることで、ごく一部ではあるけどリンク獲得の足掛かりになることもなくはない。いや、自分だったら返信来るかどうか不安になるけど……あ、逸れた。また本題戻そう。
それから、自分のウェブサイトと関連する領域や同じ産業内の別サイトでゲストブログを書けば、その記事経由で自分へのバックリンク増える可能性は十分考えられるよね。ま、それも運次第という面もちょっと否めない気がする。
リンク数そのものはいまだ重要視されている事実は変わらなくて。ただ最近じゃSEO専門家とかコンテンツ制作者も、「持っているリンク数より質」重視になってきている感じ。要するに……いや、この言葉使いたくなかったんだ。でも本音として「価値あるリンク」を目指す流れだよなあ、とぼんやり考えてしまう。ただし相変わらずシェアされやすい内容作成こそ、大事な第一歩なんじゃないかとも思ったりする。
ここで疑問湧いてこない?「良好なオフページSEOには実際どれくらいの数のリンクが必要なの?」っていう問題。答え出せる人、本当にいるんだろうか…。
最近だとソーシャルメディアの存在感が大きくてさ、誰か一人でもシェアしてくれたら、それが何となく他の人にも伝播していって――うーん、不思議な現象だけど――最終的にリンクにつながることも割とあるっぽい。SNS疲れとか言われてもいるけど、それでも拡散力は馬鹿にできない。
また、業界内の有名なインフルエンサー? 彼らにメール送ったりデジタルマーケティングで接触したりすることで、ごく一部ではあるけどリンク獲得の足掛かりになることもなくはない。いや、自分だったら返信来るかどうか不安になるけど……あ、逸れた。また本題戻そう。
それから、自分のウェブサイトと関連する領域や同じ産業内の別サイトでゲストブログを書けば、その記事経由で自分へのバックリンク増える可能性は十分考えられるよね。ま、それも運次第という面もちょっと否めない気がする。
リンク数そのものはいまだ重要視されている事実は変わらなくて。ただ最近じゃSEO専門家とかコンテンツ制作者も、「持っているリンク数より質」重視になってきている感じ。要するに……いや、この言葉使いたくなかったんだ。でも本音として「価値あるリンク」を目指す流れだよなあ、とぼんやり考えてしまう。ただし相変わらずシェアされやすい内容作成こそ、大事な第一歩なんじゃないかとも思ったりする。
ここで疑問湧いてこない?「良好なオフページSEOには実際どれくらいの数のリンクが必要なの?」っていう問題。答え出せる人、本当にいるんだろうか…。

水に浮かぶアヒル理論―外部リンク増やせば順位上昇?でも罠多し
難しい質問だなあ、これ。正直言って、競合他社のウェブサイトが持つドメインオーソリティ、つまり信頼性とか権威ってやつ?それにもかなり依存してくるんだよね。あれ…今なんの話してたっけ、ああそうだ、同じ業界で本当に争ってる相手なのか確認しなくちゃいけないってこと。うーん、一部の事業主はSEO目的でバックリンクを買ったりするし、それで自分たちのドメインが急に有名になったと錯覚したり――いや実際ランキングも劇的に上がることもあるらしいから困る。ま、それでも検索エンジン側はページランキングを不正に操作しようとする行為にはちゃんとペナルティ課すみたい。リンク構築については、やっぱり「量」より「質」重視という倫理観があるよね。その原則考えれば、自分のドメインオーソリティ上げたいだけでディレクトリサイトなんかにリンク送っちゃうと、不正行為として厳しく処罰される可能性大きいと思う。でもまあ、人間誰しも楽したくなる瞬間ってあるよな…。さて、本題戻そう。
## バックリンク
ウェブページとかウェブサイトがほかの場所からリンクされた場合、その繋ぎ目――まあそれこそバックリンクって呼ばれているものさ。えっと、このバックリンクは検索エンジン結果ページ(SERP)で順位に結構強い影響力持つ時もあるみたい。でも全部じゃないというか…いや、どうだったっけ?ともかく、多くの場合SEOやランキング向上には非常に重要視されている要素なんだろうなぁ。それぞれのウェブページやサイトごとの順位決定にはパラメータが複数絡むわけだけど、その中でも検索エンジン側が実際どこまでバックリンクを重視しているかについては…完全には分からない部分多い。ただ、ときによっては驚くほど大切扱われている場面も確かに存在する。
バックリンクそのものは信頼できる形じゃないとダメらしい。「非倫理的」とか「人工的」な方法で自分たちへのバックリンク作ろうなんて思わないほうがいい。本当に数より質なのさ…。いやほんと世知辛いよね、この世界。でも大事だから繰り返すけど、無理矢理増やしても意味なし。一歩間違えば痛い目見るだけだからさ。ま、いいか。
## バックリンク
ウェブページとかウェブサイトがほかの場所からリンクされた場合、その繋ぎ目――まあそれこそバックリンクって呼ばれているものさ。えっと、このバックリンクは検索エンジン結果ページ(SERP)で順位に結構強い影響力持つ時もあるみたい。でも全部じゃないというか…いや、どうだったっけ?ともかく、多くの場合SEOやランキング向上には非常に重要視されている要素なんだろうなぁ。それぞれのウェブページやサイトごとの順位決定にはパラメータが複数絡むわけだけど、その中でも検索エンジン側が実際どこまでバックリンクを重視しているかについては…完全には分からない部分多い。ただ、ときによっては驚くほど大切扱われている場面も確かに存在する。
バックリンクそのものは信頼できる形じゃないとダメらしい。「非倫理的」とか「人工的」な方法で自分たちへのバックリンク作ろうなんて思わないほうがいい。本当に数より質なのさ…。いやほんと世知辛いよね、この世界。でも大事だから繰り返すけど、無理矢理増やしても意味なし。一歩間違えば痛い目見るだけだからさ。ま、いいか。
良質な被リンク幻想と現実—倫理・抜け道・警告
ウェブサイトABCは、まあ、名前だけ聞くと普通のレストランの公式ウェブサイトなんだけど、実際には著名なフードレビューサイトやらブログであるウェブサイトXYZからもバックリンクを受けているんだよね。なんかこういう関係性って面白いと思わない?えっと、このケースは「倫理的で価値があって関連性も高い」バックリンクの好例とされてるらしい…うーん、少なくとも一般論ではそうみたい。でもさ、本当にそれが全員にとって理想形なのかな、とか時々考えてしまう。ま、話を戻す。
バックリンクは今でも重要視され続けていて、それゆえに多くのウェブサイト運営者が色んな非倫理的手段に頼ろうとしちゃう現実があるんだ。たぶん、焦りとか競争心とか色々入り混じってる気がする。ああ、何だっけ…えっと、その中には例えば「バックリンク売買」とか、「リンク交換ネットワークへの参加」、あとベタだけど「バックリンク購入」とかも含まれてたりする。それにしても人間って抜け道探す才能あるよね……いやまあ自分も昔ちょっと調べてたことあるから偉そうなこと言えないんだけど。
こうした方法、多くの場合は検索エンジン側から良しとはされてなくてさ。このへん曖昧な線引きあるものの、一度でも「非倫理的行為」と見なされたら、そのウェブサイトにはペナルティだったりインデックス削除みたいな措置が取られる場合が結構あるらしい。怖いよね…。でも逆に潔白なら問題ないはず—いや、それもちょっと極端かな。
ところで、「バックリンクはウェブサイト同士の会話」なんて比喩で語られることもしばしば見かける。つまり一方通行じゃなく、お互いがお互いを認識している感じというか。でもこの表現、本当にピンと来る人どれくらいいるんだろう? ま、大体そんなニュアンスなんだと思う。
バックリンクは今でも重要視され続けていて、それゆえに多くのウェブサイト運営者が色んな非倫理的手段に頼ろうとしちゃう現実があるんだ。たぶん、焦りとか競争心とか色々入り混じってる気がする。ああ、何だっけ…えっと、その中には例えば「バックリンク売買」とか、「リンク交換ネットワークへの参加」、あとベタだけど「バックリンク購入」とかも含まれてたりする。それにしても人間って抜け道探す才能あるよね……いやまあ自分も昔ちょっと調べてたことあるから偉そうなこと言えないんだけど。
こうした方法、多くの場合は検索エンジン側から良しとはされてなくてさ。このへん曖昧な線引きあるものの、一度でも「非倫理的行為」と見なされたら、そのウェブサイトにはペナルティだったりインデックス削除みたいな措置が取られる場合が結構あるらしい。怖いよね…。でも逆に潔白なら問題ないはず—いや、それもちょっと極端かな。
ところで、「バックリンクはウェブサイト同士の会話」なんて比喩で語られることもしばしば見かける。つまり一方通行じゃなく、お互いがお互いを認識している感じというか。でもこの表現、本当にピンと来る人どれくらいいるんだろう? ま、大体そんなニュアンスなんだと思う。



