ECサイトの作り方って、調べると色々な情報が出てきて、正直、何から手をつけていいかわからなくなりますよね。僕も最初はそうでした。プログラミングが必要?デザインのセンスがいる?費用はめちゃくちゃ高い?…みたいに。でも、色々試していくうちに、本質はもっとシンプルなことなんだなって気づいたんです。
まず結論から言うと
ECサイト構築で一番大事なのは、「どの道具(プラットフォーム)を選ぶか」と「法律周りをきっちりやるか」、この2つに尽きます。正直、今の時代、プログラムを書けなくても、デザインセンスに自信がなくても、立派なネットショップは作れるようになってるんです。 大事なのは、自分のやりたいことに合った道具を見つけること。それだけと言ってもいいくらい。
よくある失敗は「目的」を見失うこと
手順の話に入る前に、ちょっとだけ。多くの人が陥りがちなのが、いきなり「Shopifyがいいらしい」「BASEが無料だから」みたいにツールから入っちゃうことです。 でも、考えてみてください。趣味のハンドメイドアクセサリーを週末に10個売るのと、海外から仕入れた商品を月間1000個売るのでは、必要な機能も、かけるべきコストも全然違いますよね?
例えば、世界的に見るとShopifyは圧倒的なシェアを持っていて、特にアメリカでは市場の大きな部分を占めています。 だから海外の情報を読むと「Shopify一択!」みたいな論調が多い。でも、日本に目を向けると、BASEやSTORESみたいに、もっと手軽に始められて、国内の商習慣に強いサービスも人気です。 この違いを知らずに「世界標準だから」という理由だけで選ぶと、「こんなはずじゃなかった」ってことになりかねない。要するに、自分の「目的」と「規模」に合った道具を選ぶのが、遠回りに見えて一番の近道なんです。

ECサイト構築、具体的な7ステップ
よし、じゃあ具体的な手順の話をしましょうか。僕がいつも意識してるのは、だいたいこの7つのステップです。
- コンセプトと事業計画:何を、誰に、どう売るか。これが全ての土台。
- プラットフォームの選定:一番大事なところ。後で詳しく比較します。
- ドメイン取得:お店の「住所」になるURLですね。独自ドメインがおすすめ。
- サイトのデザインと商品登録:お店の見た目を整えて、商品を並べる作業。
- 決済と配送の設定:お客様がお金を払って、商品が届くまでの流れを作る。
- 特定商取引法に基づく表記の準備:日本の法律で定められた、超重要なページ。
- テストと公開:実際に自分で買ってみて、問題がないか確認してからオープン!
特に重要なのが2番のプラットフォーム選びと、6番の法律関係ですね。他は正直、後からでもいくらでも修正が効くので。
どうやって作る?プラットフォームの比較
さて、一番の悩みどころ、プラットフォーム選びです。大きく分けて3つのタイプがあります。どれが良い悪いじゃなくて、それぞれに得意なこと、不得意なことがあるんです。
| 構築方法 | 費用感 | カスタマイズ性 | 必要なスキル |
|---|---|---|---|
| ASPカート (Shopify, BASE, STORESなど) |
初期費用はほぼゼロ。月額無料〜数万円。でも、売上に応じた販売手数料がかかる点には注意が必要。 | テンプレートが基本。アプリで機能追加はできるけど、根本的な改造は難しいかな。 | ほぼ不要!パソコン操作ができればOK。初心者や個人には圧倒的におすすめ。 |
| オープンソース (EC-CUBEなど) |
ソフト自体は無料。でもサーバー代とか、カスタマイズを業者に頼むならその費用がかかる。トータルだと結構高くつくことも。 | かなり自由!プラグインも豊富だし、知識があれば好きなようにいじれる。 | HTML/CSSの知識はほしい。サーバー管理とか、セキュリティ対策も自分でやる覚悟が必要。 |
| フルスクラッチ (完全自社開発) |
数百万〜数千万円。青天井です。まあ、個人でやる選択肢ではないですね。 | 完全に自由自在。世界に一つだけのサイトが作れる。 | 専門の開発チームが必須。企画、設計、開発、全部の知識が求められます。 |
個人的には、ほとんどの人はASPカートから始めるのが正解だと思ってます。 まずはBASEやSTORESの無料プランで始めてみて、売上が伸びてきて、もっと色々やりたくなったらShopifyに移行する、とか。 最初から完璧を目指さないのがコツですね。

意外な落とし穴:決済と法律周りの話
サイトのデザインが完成して、商品も並べたら、いよいよ公開!…と、その前に。決済方法と「特定商取引法に基づく表記」は絶対に確認してください。
決済方法は、クレジットカードだけじゃなくて、コンビニ決済やキャリア決済、ID決済(Apple PayやGoogle Payなど)みたいに、選択肢が多ければ多いほど、お客さんの「買いやすい」につながります。 決済代行会社っていうサービスを使うと、いろんな決済方法をまとめて導入できるので便利ですよ。 どの決済方法が使えるかはプラットフォームによっても違うので、選ぶときの重要なポイントになります。
そして、もう一つが「特定商取引法に基づく表記」のページ。 これは、日本の法律でECサイトに表示が義務付けられているもので、事業者の名前、住所、電話番号などを記載する必要があります。 これがないと、法律違反になる可能性もあるし、何よりお客さんからの信頼を得られません。 ちょっと面倒に感じるかもしれないけど、テンプレートを参考にすれば難しくないので、必ず作りましょう。
作っただけでは始まらない。「公開後」が本番
多くのガイドブックはサイトを「公開」するところで終わってるけど、本当のスタートはそこからです。正直、サイトをオープンしただけでは、誰も来ません。砂漠の真ん中にお店を建てたようなものなので。
だから、公開したらすぐにやるべきことがあります。
- アクセス解析の導入:誰が、どこから、どのくらい来ているのかを知るための道具。これがないと改善のしようがない。
- 集客の初期戦略:まずはSNSで発信したり、友人に知らせたり。広告を少し使ってみるのも手。何もしなければ、売上はゼロのままです。
- 顧客対応の準備:注文が入ったらどうやって連絡して、どうやって梱包して、いつまでに送るのか。問い合わせが来たらどう返すか。この辺のフローを考えておかないと、いざ注文が入ったときにパニックになります。
売上っていうのは、「アクセス数 × 購入率 × 客単価」という方程式で成り立っています。 サイトを作っただけでは、最初の「アクセス数」がゼロ。だから、公開後はまずここを増やす努力が必要になるわけです。
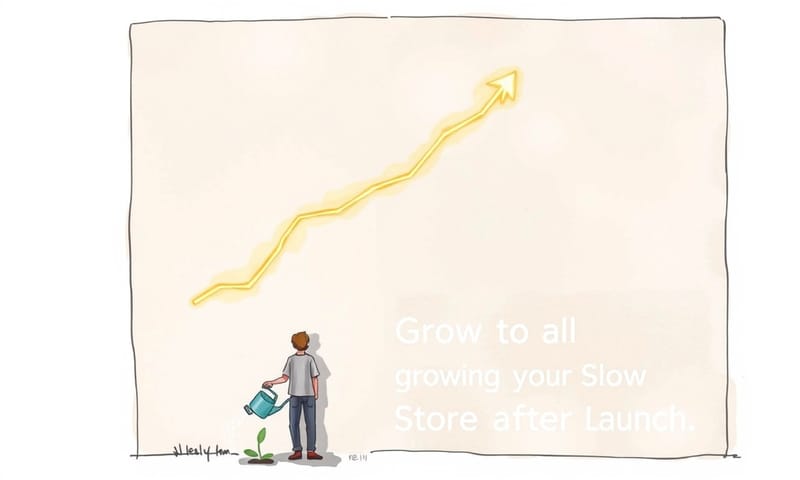
よくある間違いと誤解
最後に、僕がこれまで見てきた中で「あー、もったいないな」って思う間違いをいくつか共有しておきます。
- 間違い1:最初から完璧なデザインを目指す。
何ヶ月もかけてデザインをいじり続ける人がいますが、その間、売上は1円も生まれません。まずは最低限のデザインで公開して、お客さんの反応を見ながら改善していくほうがずっと効率的です。
- 間違い2:手数料の安さだけでプラットフォームを選ぶ。
月額費用が無料でも、販売手数料が高ければ、売上が増えるほど利益が圧迫されます。 将来の売上規模を考えて、トータルでコストを比較することが大事です。
- 間違い3:個人情報の表記を怖がる。
「特定商取引法に基づく表記」で住所や電話番号を公開するのが怖い、という人もいます。 でも、これは消費者保護のためのルール。 どうしても抵抗がある場合は、テキストではなく画像で表記するなどの対策もありますが、基本的にはビジネスをする上での責任と捉えるべきですね。 信頼がなければ、商品は売れません。
ECサイト構築は、一度作ったら終わりじゃなくて、育てていくもの。だから、最初の一歩はできるだけ身軽に、小さく始めてみるのが一番だと思います。この記事が、その最初の一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
あなたの場合はどうですか?
あなたがもしECサイトを始めるとしたら、一番のハードルになっているのは何ですか?「商品の準備」「時間の確保」「技術的な不安」など、ぜひ下のコメントで教えてください!



