夜中2時、ベッドの中でAIに相談されてるのは誰?
最近ね、「あれ、アクセスどこいった?」って静かに減ってるウェルネス系サイト、多いなって話をよく聞くんだけど。
で、よくよく聞いていくと、SEOはちゃんとやってるつもりなんだよね。「キーワードも入れてるし、記事も長いし、専門家に監修もらってるし」って。
でも、夜中2時にベッドでスマホ握ってる人たち、もう「10個の青いリンク」を1個ずつタップしてくれるほど、やさしくない。あの人たち、今なにしてるかっていうと、AIにこう言ってる。
「不安と不眠がひどい。自然な方法でなんとかしたい。薬はちょっと怖い。私の場合どうしたらいい?」
この瞬間、AIの画面の中に、誰のコンテンツが引っぱり出されて、まとめられて、引用されてるか。ここで呼ばれてないと、どれだけいい記事を書いていても、「存在しなかったこと」みたいになる。
なんかちょっと怖いけど、今ってそういうゲームになってきてる。
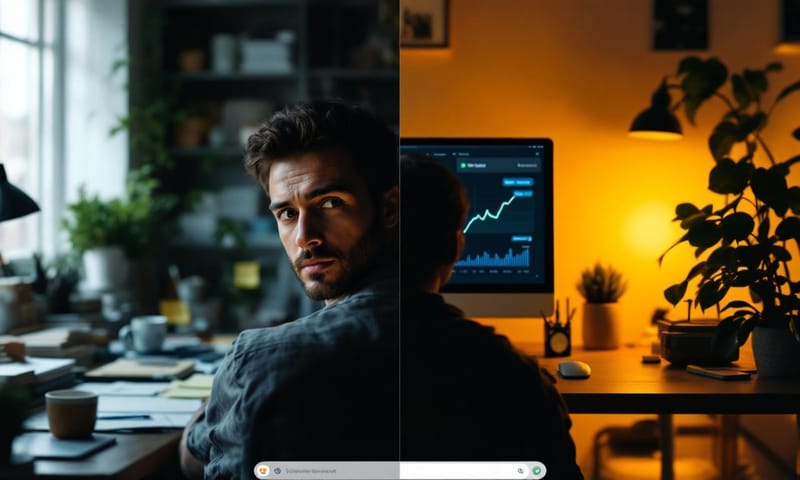
AI検索って結局なに者なのか問題
「AI検索」とか「AEO」とか「GEO」とか、カタカナとアルファベットが一気に出てきて、正直ちょっとやる気なくなる言葉たちなんだけど。
ざっくり言うと、最近の検索って、
・AIチャット(ChatGPTとか、Perplexityとか)
・音声アシスタント(Siri、Google アシスタント、Alexaとか)
・GoogleのAIオーバービューみたいな「最初にまとめてくれるやつ」
こういう「質問したら、その場でまとめて返してくれる子たち」のことをまとめて相手にしないとダメになってきた、って話。
昔みたいに「初心者 ヨガ クラス 東京」とかじゃなくて、
「ヨガ初心者で、体固くて人目が気になるんだけど、あんまり見られないクラスない?あと10代でも浮かないところがいい」
みたいな、ほぼ友だちへのLINEみたいな聞き方が、もう普通になってきてる。これを拾ってるのが、Geminiだったり、ChatGPTだったり。
で、AIはどこから情報を持ってくるかというと、結局ふつうの検索エンジン(Google、Bingとか)+学習データ+外部の信頼できそうなサイトたち。
つまり、ふつうのSEOをサボると、AIにも見つけてもらえない。でも、SEOだけやってても、「AIが引用しやすい形」になってないと、やっぱり呼ばれない。
この両方を意識するのが、AI検索最適化、っていうちょっと長い名前のやつ。
キーワードじゃなくて「友だちへの愚痴」に近づいてる
前に検索ログをいろいろ眺めてたことがあって、「ああ、もうこれはキーワードじゃないな」と思ったのが、こんな感じのやつで:
・「生理前になると急に不安定になる 仕事に支障出る とりあえず今日なんとかしたい」
・「30代後半 女 仕事やめたい 疲れた 健康ボロボロ でもお金不安」
こういうの、昔のSEOっぽく「PMS 対処法」とか「バーンアウト 30代」みたいなキーワードだけ狙って書いてると、半分しか拾えない。
AIに聞く人って、「今の自分の状況」をそのまま投げてくる。年齢、性別、気持ち、条件(薬はいや、家でできることだけ、予算これくらい)まで、一気に。
だからコンテンツ側も、
・「不安 対処」じゃなくて、「夜中に目が覚めて、そのあとずっとスマホ見ちゃうときにできること」
・「睡眠の質 改善」じゃなくて、「子どもが寝たあとしか自分の時間ない人向けの、15分以内でできる睡眠ルーティン」
みたいな、「状況ごとに答える」書き方の方が、AIにも人にも刺さりやすい。
AIが拾いにくいウェルネス記事の、よくあるつまずき
いろんなウェルネス系ブログを読み漁ってて、「もったいないな」と感じたパターンがいくつかあって:
・肝心の答えが、だいぶ下の方に埋まってる
・見出しがふわっとしてて、AIから見ると「どこが何の話か」わかりにくい
・更新日が古いまま放置されてる
・誰が書いてて、どんな経験がある人なのか、よくわからない
AIって、人間以上に「構造」を見てる感じがあって。
たとえば「ストレスで眠れないときの対処法」を聞かれたとき、
・記事の冒頭で、すぐに「これが結論です」と言ってくれてるか
・「原因」「今すぐできること」「医療機関に相談したほうがいいサイン」みたいに、整理された見出しになってるか
・著者や監修者が、実際にその分野で経験積んでる人なのか
こういうところをまとめて見て、「ここから引用しよう」と決めてるっぽい。
Googleがよく言うE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の話も、ただのスローガンじゃなくて、AI側から見ると「このサイト、本当に大丈夫そう?」をチェックする指標になってる。
AI検索の世界で生き残るために、正直これだけはやっときたい
なんか全部やろうとするとしんどいから、「ここをいじると一気にAIに拾われやすくなるよね」ってところだけ、ざっくり出してみるとこんな感じになる。
・人としゃべるみたいな文章にする
・AIが読みやすいように、見出しと箇条書きで骨組みをはっきりさせる
・「これはFAQですよ」「これはレビューですよ」って機械に伝える印(スキーマ)をつける
・画像や図解を、AI検索でも役立つ形でちゃんと用意する
・質問と答えのセットで、ニッチな疑問に答えておく
・サイトの外側でも「このブランド、よく見るな」と思われるようにしておく
これだけ書くとふわっとしてるから、ちょっと具体的な話も混ぜる。
| やりがちパターン | AIから見たときの困りごと | ちょっとマシになる方向 |
|---|---|---|
| 専門用語多めで、かっこいいけど難しい文章 | 意味は取れるけど、「誰に向けて、どんな状況の答えか」がぼやける | 中学生でも読めるくらいの言葉に落としつつ、「どんな人向けか」をちゃんと書く |
| 長いイントロで背景説明が続く | 「この質問への答え」がどこから始まるか、機械的に切り出しにくい | 最初の見出し直後に、結論と要点を先に置いておく |
| 見出しが「はじめに」「まとめ」だけ | どの段落が「対処法」で、どれが「注意点」なのか区別しづらい | 「今すぐできること」「病院に相談すべきサイン」みたいに中身がわかる見出しにする |
| 更新日が2年前で止まってる | 最新情報を優先したいAI側からすると、ちょっと選びづらい | 内容を見直して、変わってない部分も含めて更新日をちゃんと反映する |
| 著者情報が「運営チーム一同」みたいなざっくり表記 | どんなバックグラウンドの人が書いたのか、信頼の判断がしづらい | 専門分野や経験年数を含めたプロフィールと、監修者情報を載せる |
そういえば、海外と日本でAI検索の「重さ」も少し違う
英語圏の話を見ていると、OpenAIのサービスを毎週使っている人が世界で4億人以上いるっていう数字が出ていて、そこからウェルネス系の相談もかなり流れ込んでるらしい。
アメリカだと、Gen Z とミレニアル世代が健康情報を探すときに、最初からAIに投げる割合が高くて、そのままサプリとかフィットネス商品の購入までつながることも多いっていう調査もある。
一方で日本だと、厚生労働省とか自治体の公式情報もかなり重視されるから、「AIで見たこと」と「公式サイトで確認したこと」の両方を見て判断する人が多い感じがする。
だから、海外向けのウェルネスブランドだと、「AIの中で目立つこと」と「Amazonやレビューサイトでの存在感」をがっつり取りにいく戦いになりがちだけど、日本のブランドだとそれに加えて、
・公式ガイドラインと矛盾しない表現にする
・自治体や医療機関の情報へのリンクをちゃんと貼る
・「これは一般的な情報で、診断ではないですよ」と明確に書く
みたいな、「安全側」に振った作り込みもセットで必要になる。

じゃあ、具体的に何を書き換えればAIに拾われやすくなる?
細かいテクニックを一気に並べるより、「こういう気持ちで書き直すとだいぶ変わるよ」という方向で整理したほうが楽かもしれない。
1. まず、人にしゃべるみたいに書く
「ストレス軽減のための方法論を実装しましょう」みたいな言い方より、
「正直、今しんどいときに、これだけやっとけば少しラクになるよって話をするね」
くらいの方が、AIも「これは悩んでる人向けの答えだな」と認識しやすい。
それと、質問そのものも、ちゃんと記事の中に入れておくといい。
・「夜中に不安で目が覚めて、そのあとスマホをずっと見ちゃうとき、どうしたらいい?」
・「薬に頼りたくないけど、不安と不眠を少しでもラクにしたい」
こういう「そのままAIに投げられそうな聞き方」を見出しや本文に入れておくと、AI側が「これはこの質問への回答部分だ」と理解しやすくなる。
2. 構造をちゃんと「見える化」する
AIは長文が嫌いなわけじゃなくて、「どこからどこまでが何の話か」がわからないのが苦手。
だから、
・見出しでテーマをはっきり書く(「原因」「今すぐできること」「医師に相談すべきとき」など)
・箇条書きで要点を区切る
・比較があるなら、表でまとめる
・メリット・デメリットを分けて書く
こういう地味なことが、AIにとってはすごくありがたい。
3. スキーマで「これはFAQだよ」って教えてあげる
コードの細かい書き方は置いといて、「ラベルを貼る」というイメージだけ持っておくと楽。
・サービスのページには「サービスですよ」ってラベル
・店舗情報には「ここが住所ですよ」ってラベル
・よくある質問には「FAQですよ」ってラベル
・商品ページには「商品ですよ」ってラベル
こういうのを、構造化データ(スキーマ)で表現しておくと、AIも検索エンジンも、「あ、これは◯◯の情報ね」とすぐわかる。
4. 声で聞かれても答えられるようにしておく
散歩中とか、料理しながらとかに、「ねぇSiri、近くで肩こりのマッサージできるところ教えて」みたいな感じで聞かれるケース、結構多い。
そのときに拾ってもらうには、
・「◯◯駅から徒歩◯分」「駐車場あり/なし」「営業時間」みたいな情報をはっきり書く
・質問文そのままの形でQ&Aを作っておく
・「はい/いいえ」で答えられる質問も混ぜておく
こういう、ラジオでしゃべるみたいなイメージの書き方が効いてくる。
5. 画像も「ただの飾り」じゃなくて、情報として置いておく
Perplexityとか一部のAIツールは、回答に画像も出してくることがあって。
・ストレッチの手順が一枚でわかるイラスト
・呼吸法のリズムがパッと見でイメージできるビジュアル
・生活習慣を変えたビフォー・アフターの雰囲気写真
こういうのがちゃんとページにあると、「視覚的に説明してるページ」としても価値が出る。
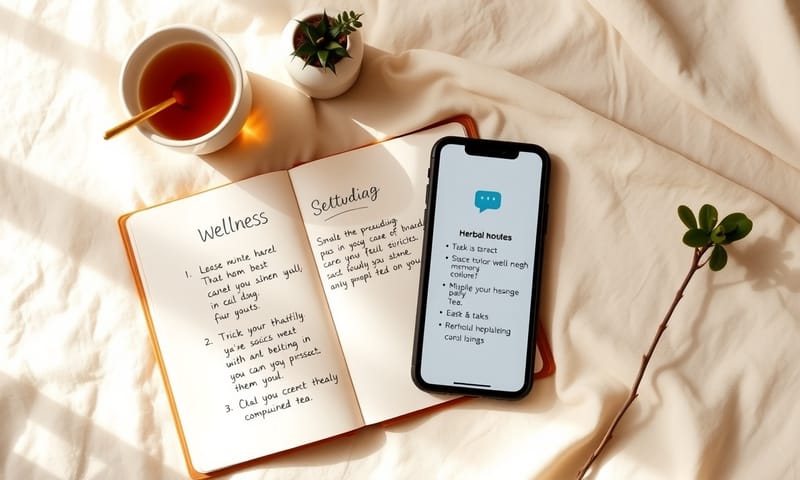
6. サイトの外でも「この人、よく見るな」と思われるようにする
AIは、一つのサイトだけ見てるわけじゃなくて、「この名前、あちこちで見かけるな」「この人、専門家として紹介されてるな」というのもちゃんと見てる。
・Googleビジネスプロフィールや、医療・ウェルネス系のディレクトリで情報をそろえる
・口コミサイト(日本だとEPARKとか、美容系ならホットペッパーとか)での評価を積み上げておく
・他のメディアに寄稿したり、インタビューに出たりして、名前を出しておく
・小さくてもいいから、自分たちでアンケートや簡単な調査をして、その結果を公開しておく
こういう「外側の証拠」が増えると、「このブランド、AIの中でも信用してよさそう」と判断されやすい。
AI検索の成果って、どうやって追えばいいのか
正直、「AIの中で何回名前出されました」みたいなメーターが、まだ完璧な形では存在してない。
でも、できることはいくつかあって:
・自分のブランド名や記事のテーマを、ChatGPTやPerplexity、GoogleのAIオーバービューで定期的に検索してみる
・AIに「この情報の出典は?」と聞いてみて、どのサイトを挙げるかチェックする
・自分のURLを、AI要約系のツールに入れて、「要約」「説明」みたいなボタンが出るか試してみる
・Googleサーチコンソールで、AIモードやAIオーバービュー由来のトラフィック指標を少しずつ追ってみる
完璧な数字は出なくても、「前より名前が出るようになったか」「AIに聞いたときの答えの質が変わってきたか」を、3か月おきくらいに見ていくと、じわっと変化が見えることが多い。
正直なところ、ここだけはやっておくと後で楽になる
全部一気にやろうとすると、たぶん途中で嫌になるから、「これは最初の8ステップとして、どこかにメモっとくといいかも」というのを並べると:
1. いまのコンテンツをざっと見直して、「AIに引用されそうな形になってない記事」をピックアップする
2. 「よく聞かれる質問」を、ちゃんとQ&Aの形でまとめたページをつくる
3. サービスページや店舗情報、口コミページに、最低限のスキーマ(ラベル)を入れる
4. Googleビジネスプロフィールと、主要なディレクトリの情報をそろえる
5. 情報が古くなってる記事を、データごと更新していく
6. 「ニッチだけど、実際によく聞かれる悩み」に絞った記事を、少しずつ増やす
7. 自分のテーマについて、SiriやGoogleアシスタントに質問してみて、誰が答えてるかを見る
8. 3か月ごとに、AIに自分のブランド名を聞いてみて、答えがどう変わったかメモしておく
このあたりから手をつけておくと、「気づいたらAIにまったく触れられてない」という状態は、だいぶ避けやすくなるはず。
言ってしまえば、「AIに親切なウェルネス記事」ってこういうやつ
ちゃんと調べた人たちの話を見ていると、AI経由のコンバージョンって、ふつうのGoogle検索からのクリックより3〜7倍くらい高くなるケースもあるらしい。
理由はたぶんシンプルで、「もう相談したあとだから」。AIに悩みを話して、そこから紹介されるってことは、すでに気持ちがある程度整理されていて、「あとはどこにお願いするか」モードになってる。
だから、ウェルネスブランド側からすると、
・人に話しかけるみたいな文章で
・AIにも人にも構造が見える形で
・誰がどんな経験から書いてるかがわかるようにして
・サイトの外側でも、ちゃんと存在感を出しておく
こういう、すごく地味な積み上げが、数か月後の「AIに呼ばれる回数」につながってくる。
スタートアップでも、個人のコーチでも、ヨガスタジオでも、「AI検索に好かれるかどうか」はもう避けて通れないところに来てるから。
今のうちに、「夜中2時にAIに相談されたとき、自分の言葉がそこに混ざってる状態」を少しずつ増やしておくのが、たぶん一番コスパがいい。
ここまで読んだあなたに、ひとつだけ聞いてみたい
AI検索、もう自分のブランド名で試してみたことあります?
もしよかったら、「どんな質問を投げたか」と「どんな答えが返ってきたか」、どこかにメモしておいてほしい。そこから次に直したい記事とか、「この悩みはちゃんと拾っておこう」ってテーマが、結構はっきり見えてくるはずだから。



