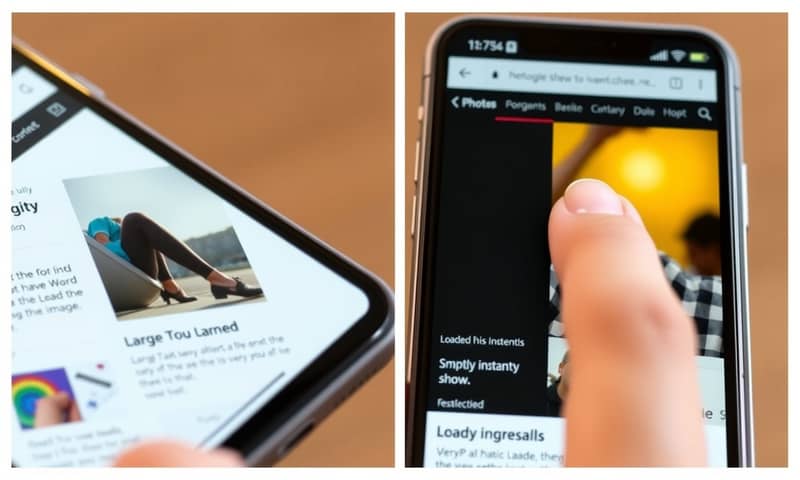WebP... 最近よく聞く。Googleが作った、ウェブ向けの画像フォーマット。 表示が速くなるから、SEOにも良い、と。 でも、本当のところはどうなんだろう。ただ変換すればいい、ってものでもないはず。
今日はそのあたりを、ちょっと整理してみる。自分用のメモに近いかもしれない。
まず結論から言うと
WebPは、SEOに「間接的に」効く。 これが今のところの感触。直接、順位が上がる魔法じゃない。
要するに、こういうこと。
- WebPは画像が軽い。JPEGに比べて25~34%くらい軽くなるらしい。
- 軽いと、ページの表示が速くなる。特にスマホ。
- 表示が速いサイトは、ユーザーが離脱しにくい。体験が良い。
- Googleは、ユーザー体験が良いサイトを評価する。 Core Web Vitalsとか、そういう話。
だから、結果的にSEOにプラスに働く。 でも、導入の手間とか、いくつか考えないといけない点もある。そこが大事。
じゃあ、どうやって導入するのか
やり方はいくつかある。単純に画像を変換するだけじゃ、古いブラウザで表示されない問題があった。 今はもう、ほとんどのブラウザが対応してるけど。 2024年時点で、全体の97%が対応済み、みたいなデータもある。
それでも、念のため、非対応ブラウザへの配慮は必要。 その方法としては...
- 変換ツールを使う。 Google自身が「Squoosh」っていうWebツールを出してる。 画像をドラッグ&ドロップして、画質を調整して、ダウンロード。簡単。
- WordPressなら、プラグインがある。 アップロードした画像を自動でWebPに変換してくれるやつ。 これが一番楽かもしれない。いちいち手作業しなくていいから。
- HTMLで書き分ける。
<picture> <source srcset="image.webp" type="image/webp"> <source srcset="image.jpg" type="image/jpeg"> <img src="image.jpg" alt="代替テキスト"> </picture>この書き方なら、WebP対応ブラウザはWebPを、非対応ブラウザはJPEGを読んでくれる。 これが一番丁寧な方法。
日本のサイトだと、まだ古い環境をサポートしてる会社もあるから、この
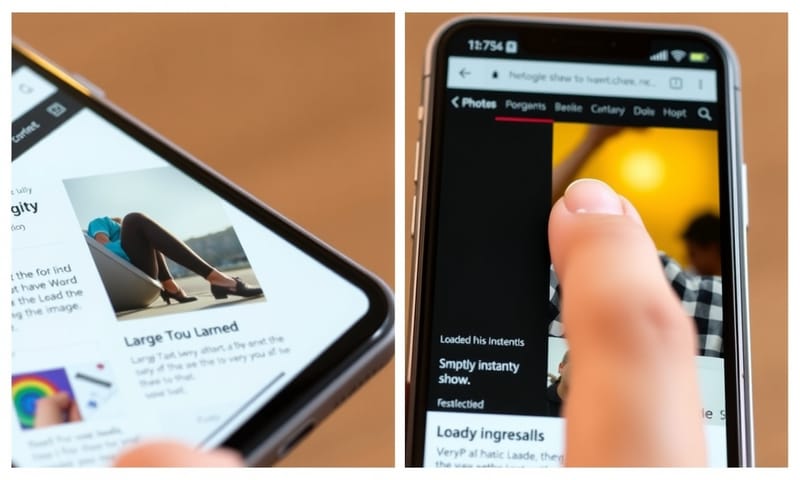
知っておくべきデメリットとか、注意点
良いことばかりじゃない。少し立ち止まって考えるべき点。
- 変換の手間。 結局、これが一番大きい。既存の画像を全部WebPにするのは、かなりの作業。自動化の仕組みがないと、現実的じゃない。
- 画質は本当に同じか? 「画質を保ったまま」ってよく言うけど、非可逆圧縮である以上、厳密にはデータは失われてる。 写真家とか、デザインにすごくこだわるサイトだと、圧縮率を上げすぎると、違いが気になるかもしれない。この辺は、自分の目で見て判断する必要がある。
- 画像を保存したいユーザー。 サイト上の画像を右クリックで保存するユーザーもいる。その時、.webpファイルだと、PCの古いビューワーで開けないことがある。 これで「うざい」って感じる人もいるらしい。 ターゲットユーザーによるけど、一応頭に入れておくべき。
JPEG、PNG、WebP…結局どれがいいの?
まあ、ケースバイケースなんだけど。僕なりの使い分けはこんな感じ。
| JPEG | PNG | WebP | |
|---|---|---|---|
| ファイルサイズ | まあまあ。でも高画質にするとすぐ重くなる。 | 重い。特に写真だとファイルサイズがすごいことに… | 軽い。これが最大の取り柄。JPEGより25-34%軽いとか。 |
| 背景透過 | できない。背景は白か黒か、何か色で埋めるしかない。 | これが得意技だった。昔は。 | できる。PNGの代わりになれる。 |
| アニメーション | 無理。 | APNGっていうのもあるけど、主流じゃない。 | できる。GIFの代わりにもなる。 |
| 個人的な使い方 | もうあまり積極的には使わないかな…。過去の遺産。 | どうしてもPNGじゃないとダメ、って場面は減った。 | 基本、これ。写真もロゴも、まずWebPを検討する。 |
| 気になる点 | とにかく表示速度がボトルネックになりがち。 | ファイルサイズ。本当に、すぐ大きくなる。 | 変換の手間。あとはAVIFっていう、さらに新しいのが出てきてるのが気になる。 |
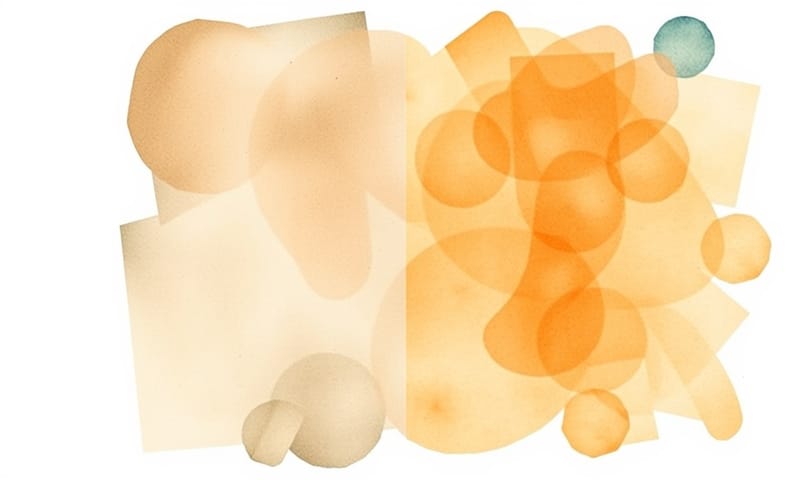
次世代フォーマットの、さらに次
WebPが「次世代フォーマット」と呼ばれて久しいけど、実はもう次のフォーマットも普及し始めてる。AVIFっていうやつ。
AVIFは、WebPよりもさらに圧縮率が高いらしい。 ただ、対応ブラウザとか、ツールとか、まだWebPほどは普及してない印象。 2024年時点では、WebPが一番バランスが取れてて無難な選択肢、って感じかな。 でも、数年後にはAVIFが主流になってるかもしれない。この辺の動向は、ずっと見ておかないと。

【簡易チェック】WebP、導入すべき?
最後に、自分用の思考整理として。こんなサイトは、導入を真剣に検討する価値がある。
- 画像がたくさんあるサイト(ECサイト、ブログ、メディアサイトなど)
- PageSpeed Insightsで「次世代フォーマットでの画像の配信」と指摘されているサイト
- モバイルユーザーが多いサイト
- 表示速度がコンバージョンに直結するサイト
逆に、数枚しか画像がないコーポレートサイトとかだと、手間をかけてまでやる効果は薄いかもしれない。費用対効果の問題。
結局は、自分のサイトの目的と、かけられるリソース次第、ということか。
あなたはどう思いますか? WebP導入の最大の壁って、やっぱり「変換の手間」だと思いますか?それとも「画質へのこだわり」? よかったら、あなたの考えも聞かせてください。